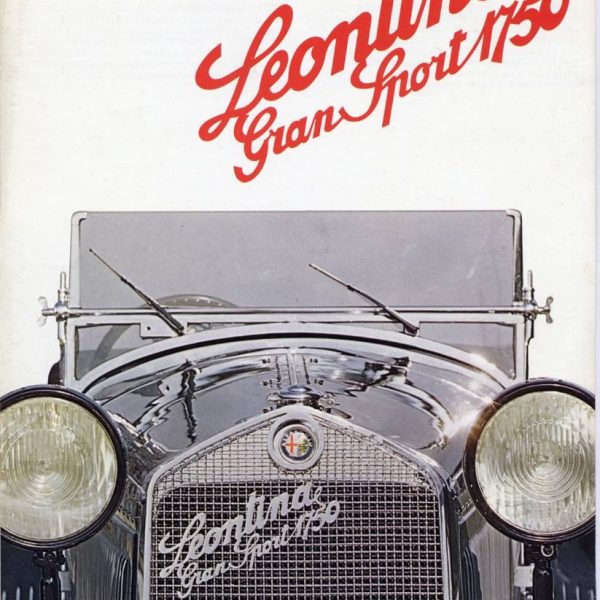ドローンを知ると世界がわかる #03
J.ハイド 2022.09.21
 ついにスタートするライセンス制
ついにスタートするライセンス制
写真家、J.ハイドです。2022年12月、以前から話題となっていたドローンのライセンス制度が正式にスタートします。(以下、本記事は2022年9月の公開時点の情報に基づき記載されています。)
またこれに先立ち、6月20日からは100g未満の言わばマイクロドローンを除き、ほぼ全ての機体が登録制となりました。6月20日時点で登録をしていない機体には、今後、リモートID機器の搭載が必要であり、そして機体には登録番号の明記が義務づけられます。個人のライセンスに関しては、従来から国交省が各団体を通じていくつかの資格制度を認可しています。それらの取得者に関しては、アップデートの更新研修を受ける事で正式なライセンスが発行される模様です。
ドローンパイロットに興味がない方にはほとんど知られていませんが、現在日本でドローンを運用するには、国土交通省が管轄する「ドローン情報基盤システム」、通称DIPSにて操縦者登録と機体登録を行い、包括申請にて航空局の許可を取っておくことが一般的です。これによって通常ドローンが飛行できない人口密集地区いわゆるDID地区での飛行が、原則として認められます。
しかし、それだけではすぐに飛行しても良いものではありません。
飛行に際して、今度は「ドローン情報基盤システム 飛行情報共有機能」、通称FISSへの飛行計画登録が必要になります。もっとも完全にクローズされた空間、例えば体育館などの屋内であれば特に以上のような申請や登録は必要ではなく、屋外であってもDID地区外であれば、原則としては自由に飛行が認められています。
しかし、ドローンの飛行安全性を真摯に考え、例え最新型であっても、運用の問題や電波障害などで万が一の墜落、そして他人の身体的財産的被害が出る可能性を考えた時には、二つの情報基盤への登録は必要不可欠であると考えます。
また、DID地区であれば飛行計画を書面で作成し、飛行区域の警察や港湾関係者に届けるなどの準備を怠るべきではありません。
実はドローンの飛行はかなり目立つので、気がついた住民が警察に通報する事が多々あります。趣味での飛行であれば中止すれば良い訳ですが、撮影業務の場合は納期があり関係者も多いため、中止になる事態はできるだけ防がなければなりません。そのためにシステム登録以外の現地でのケア、いわゆる根回し的な報告が必要になります。そのためにも飛行計画書は、準備した方が良いわけです。

 規制に見られるお国柄
規制に見られるお国柄
ところが海外になると、国ごとに事情は変わってきます。まず欧米のほとんどの国で登録制度が導入されています。筆者が過去に調べた国で、再度2022年9月の最新状況をリサーチしました。
フランスでは、観光資源の保全という理由もあってか、主要都市や観光地のほとんどのエリアで飛行や撮影ができません。地元の専門業者でなければ、撮影はほぼ不可能と言えるでしょう。DJIに匹敵した「パロット」社という民生ドローンメーカーを持っているフランスですが、規制の厳しさは、やや意外です。規制が厳しいのと比例してか、同社がDJIを上回る機種を開発できないのも頷けます。
英国では、空港閉鎖に至ったドローン事故があったにも関わらず、いくつかのエリアで飛行が許可されています。自己責任や契約を重視するからか、登録さえ行っていれば比較的寛容な国と言えます。
また先端技術を好むドイツでは、本コラムでも何度も取り上げたDJIの最新型機のMAVIC 3が、「C1ドローン」の初の認定を受けるという発表が、この8月にありました。この「C1ドローン」認定によって欧州のいくつかの国では、テスト飛行を含む難しいライセンスが免除され、オンラインで取得できるライセンスで許可されると言われています。
まとめると、国によって緩和の方向もあるとはいえ、欧州では現地の協力を得なければドローンの飛行は難しいという認識が正解でしょう。比較すると日本も現状はほぼ同様か、ライセンス制度が本格的に始まると取得や申請には日本語の障壁もあるので、世界的に見てもかなり「厳しい国」となるでしょう。
一方で、ドローンに比較的寛容な国もあり、筆者が本稿で撮影したのは2019年オーストラリアのメルボルン近郊です。当時から、政府によるドローン飛行に関するアプリが整備され、ルールも明快に示されていました。しかし登録義務が必要な機体は、なんと2kg以上とされています。つまり全てのMAIVICシリーズは登録不要です。(2022年9月現在)もちろん規制区域はありますが、多くの公園や港湾エリアで少し離れたところに離発着に必要十分なスペースも確保しやすい環境です。そのため2019年当時、半日でメルボルン南東部と南西部の港、そしてウエストゲート・パーク内のピンクレイクと3エリアの撮影が実現しました。これは初めて訪れる海外の観光地としては画期的だといえます。
その後も基本的な飛行ルールや、個人で飛ばす場合と商用目的の場合で分けられる、などの大きな概要は変わっていないようです。
そしてこのような寛容な背景からか、すでにGoogleの親会社であるアルファベット傘下の「ウィング」社が、首都キャンベラとクイーンズランド州ロガンの2都市で、大規模なトライアル営業を始めています。結果、未だ実証実験を繰り返してばかりの日本とは、大きな差が出来つつあります。

 ドローン保険に見る日本の先駆性
ドローン保険に見る日本の先駆性
海外でドローンを飛行させる場合、規制以外に注意すべき点は保険です。DJIの機体には購入して実際に運用するタイミングから1年間無料で年間1億円までの損害保険が付帯しています。が、それはあくまで日本国内のみの話です。クレジットカードに付帯する損害保険でもある程度のカバーはされていますが、金額的に巨額になった場合にはその範囲を超える可能性も少なくありません。
従って、フライトを行う場合は海外での飛行をカバーする保険に改めて加入するべきだといえます。こちらも数社で様々な保険が販売されていますが、筆者がおすすめするのは東京海上日動が引き受ける「ドローン保険」です。対象機種や補償範囲が明快であり、機体や海外利用をカバーする損害賠償の契約など、柔軟かつスピーデイーに手続きできる保険となっています。掛金も年間でさほど大きな金額ではないことから、業務で運用するパイロットとしては、ぜひ検討したい保険です。
それでも保険金額はより少なくしたい、自分はあくまで決まったエリアを趣味で飛ばすだけ、という方も多いと思います。その場合は国内だけの運用になりますが「一般財団法人 日本ラジコン電波安全協会」への操縦士登録とホビー用ラジコン補償制度への登録をおすすめします。
こちらはあくまで「趣味」に限定されますが、2年間の登録費用5500円で同じ期間、賠償金1億円までが保証されます。この「日本ラジコン電波安全協会」は現在の2.4GHzがラジコン用に割り当てられた1984年に発足し、今に至っています。さらに付け加えると、手元の「ラジコン技術」誌では、その8年前の1976年に、この前身になったと思われる日本航空協会の制定する「模型飛行士登録規定」の記事が掲載されています。
その中で「第三者賠償」が規定されており、登録者には1事故あたり2000万円を限度額として「日本航空協会が契約する団体賠償責任保険に同時に加入したものとする。」とされています。
この頃、ドローンは影も形もなかった訳ですが、ラジコン飛行機の運用に関して、約半世紀前の日本の先人たちの慧眼、先駆性を裏付ける事例と言えるでしょう。
次回は、より具体的な撮影での注意点に関して、筆者の経験を交えてレポートします。