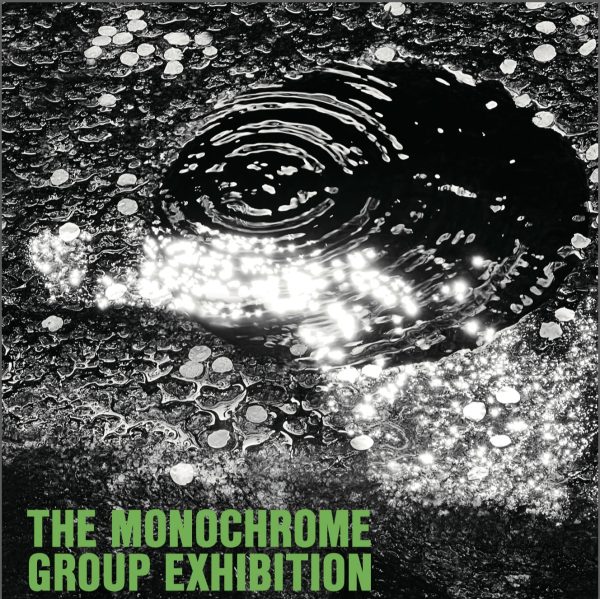ヒマラヤの麓、道なき道を駆け抜けろ! 「モト・ヒマラヤ 2022」#08
田中 誠司 ロイヤルエンフィールド・ヒマラヤ 2023.04.18
 砂煙を上げて
砂煙を上げて
素晴らしい、というか日本では物理的に経験できない星空を楽しんだ翌朝、旅の最終日は遊牧民のように砂混じりのダートを走ってこの地方唯一の都市、レーに帰る道のりだった。




途中の砂地では腕の立つ参加者が自由闊達にヒマラヤの持つポテンシャルを最大限に発揮させていた。
砂地の坂をどこまで高く上がれるか? そんなアトラクションを楽しんでいた。


筆者はといえば、砂地に慣れず高山病の後遺症でライディングへの集中力も衰えていた。
砂の深いところで、この日は3度転んだ。あとから追ってきてくれたスタッフのジェティンが引き起こすのを手伝ってくれた。
タイヤの専門家の岡本さんが「ここなら空気圧を少し下げたほうが走りやすいですよ」と、さっそく調整してくれた。
余裕のある人というのは本当に頼りになる。





旅の後半、前にも述べたが、植生限界を超えた山々の色のバリエーションが著しかった。紫色の山ってなんだ?
山の向こうには万年雪が白く輝いている。



ロイヤルエンフィールドの旅のリーダー、アジェによれば、モト・ヒマラヤが最初に開催されたのは2017年だ。当初はブレット500というモデルを用いたが、その翌年からヒマラヤを使うようになった。コースはその頃から変わらず、全長1000km程度で毎年続けられている。
2013〜14年くらいまでは、この地域の路面の舗装状態は非常に悪く、バイクでヒマラヤへ訪れることはとてもヒロイックで、達成感のある記念的な出来事だった。
それ以前、20年ほど前からロイヤルフィールドはヒマラヤに世界のライダーを招いてモーターサイクルに乗せるプログラムに携わっていたが、当時は道路も宿泊施設も充分なキャパシティーがなかったので、多くの人数をサポートできず、代わりにプライベートで走る人々が多かったという。
この土地を走るモーターサイクルのほとんどがロイヤルエンフィールドであるのは、頑丈で簡便な構造に加えて、他のメーカーのバイクでは部品の調達も難しいのが理由だという。
アジェによれば、この辺の道路の開発は当分終わらないだろうという。なぜならこれは「侵略道路」だからだ。建築にあたる組織、「BRO」はボーダー・ロード・オーガニゼーションの略である。軍務のために、必要な要件に合わせて作っては壊してを繰り返し続けている。
そして我々は再びレーの街に戻ってきた。

感極まる参加者も。このあと述べるが、標高5,000mの奥地を走り抜けるというそれだけでもう大変だし、そのための準備もなまなかなことではないのである。そうしたすべてを乗り越えた結果のゴールなのだ。



バックミラーを結ぶ形で張られている旗は、タルチョというらしい。5色の小さな旗にはそれぞれ思いが込められていて、ひとつひとつの小さな旗がはためくたびに祈りが叶う、と信じられている。
とにかく完走、というのが願いであったから、それは見事成就された。ぼくはバイクに貼ってあったゼッケン9をすべて丁寧に取り外し、スーツケースやらヘルメットに移植した。
こんなアドベンチャーを何事もなく走り続けられたのは、それは本当に幸運としか言いようがない。



夕刻の閉会式ではそれぞれの参加者に完走証が手渡された。参加者の我々は、地元のTシャツ製作会社に頼んで記念のTシャツをスタッフたちのために誂えてもらった。



あのカレーばかりの食事には辟易したが、インドを去ってみると、香りのあるインド米というのは日本ではなかなか味わえないものなのだ。
カレーはなんとなく調味料でごまかせるけれども、米の香りは味わうことができない。
そういった断片的な記憶が、旅の思い出になるのだろう。

ロイヤルエンフィールド・ヒマラヤの、標高の高いところではとても非力なエンジン、しかしスロットル開度に合わせて健気にパワーを供給してくれる従順さ、そして、パワーのわりにはしっかりしたシャシー、コンディションを選ばず楽しく走れるタイヤの組み合わせは、本当に徹底的に練り上げられた設計の成果なのだと思う。
次回、番外編として、旅を完走した最後に、番外編としてインド旅行のための準備について紹介する。僕ほど神経質にならなくてもいいのかもしれないけれども、まあたとえばお腹を壊さないようにするにはどうすればよいのか? 自分が打った手について紹介したい。