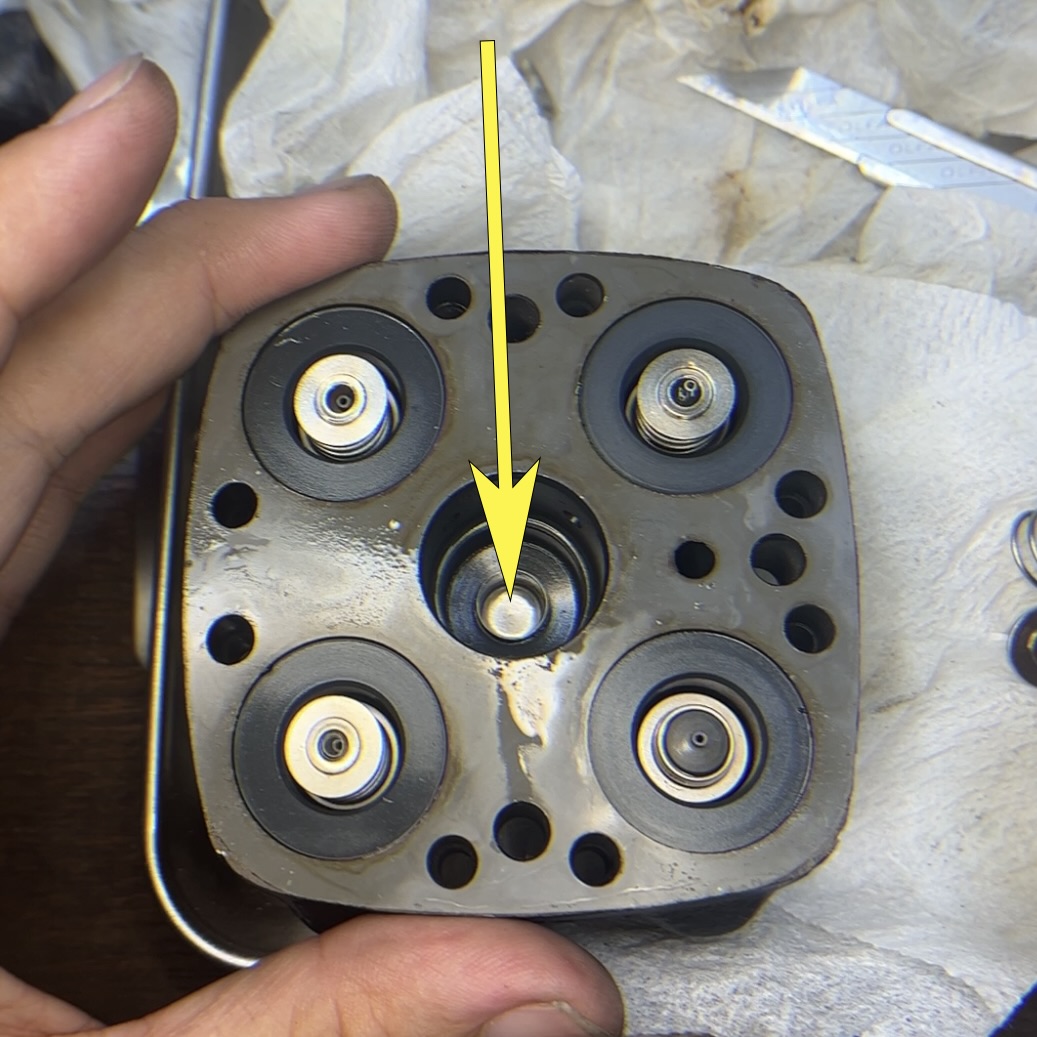『Where We Are ― ヤマハデザイン研究所60周年企画展 ―』を過ごして思うこと
楽器という「機能美」を愛でるアプローチ
安齋利晃 2024.03.29
 機能美を、もっともあらわすもの ―逗子にて、Fさんとの会話から
機能美を、もっともあらわすもの ―逗子にて、Fさんとの会話から
「機能美を、ほぼ完全なかたちにしているものはご存知ですか?」。
逗子の木漏れ日がさす一室で、Fさんからご教授を受けるなかでの問いかけには、いささかの戸惑いをもった。鉛筆などの筆記用具もそうであるし、飛行機にしてもそうだ。いろいろと思い浮かべる。
「私は楽器と思いますよ。心に響き、その造り込まれた姿を眺めることでもワクワクします」。
音階、音色によって様々な楽器を一堂に、観て、聴いて、響きを体で感じられるのは、オーケストラだ。現代の楽器のデザインは、ほぼバロック時代に完成されて、作曲家たちの名曲が、優れた音楽家によって、今に再現されて聴き入ることができる。幾重の重なる旋律が調和された響きとなって心が動かされる。
数世紀に廃れることなく、現在に在って、心動かす「道具」にある機能美を、Fさんは話されたのだ。
私の家にも、アップライトのピアノがあって、その佇まいを見ていても、心地よさという贅沢な気持ちになる。「ピアノ・ブラック」の塗装、白鍵と黒鍵からなる88の音階、天蓋、響板を開ければ、その規律ある構造に美しさを感じる。奏でられる音色のための構造が形づくる姿にも、心が動かせる。
インナーガレージを持つ方であれば、愛着持つ一台を、リビングから見る幸せな気持ちに近しい感覚だろう。
楽器にも、そうして視覚的に幸せな気持ちにさせる力があるのは、経験則からも言えることだ。
 もう一つの「楽器がある生活」へ。23年秋の六本木
もう一つの「楽器がある生活」へ。23年秋の六本木
連載『Start of Scratch』でおなじみの高梨廣孝さんから『Where We Are ― ヤマハデザイン研究所60周年企画展 ―』のお誘いをいただき、会期(2023年10月21〜23日)の前に、AXISギャラリーに伺いました。
「デザイン」が舶来品と感覚が強かった頃の1963年に、ヤマハ株式会社のインナーデザイン部門として、ヤマハデザイン研究所が設立されて、2023年は60周年。
日本楽器を前身とする同社において「楽器の伝統と文化」を尊重し、その本質を忘れることなく革新を目指すクリエイションをしています。
例えば、電子ピアノ「Clavinova」、デジタル音源とシンプルさを追い求めた「サイレントシリーズ」では、そのカタチに、同研究所が目指すものが表れています。
高梨さんは、研究所所長として1969〜1996年に在任されていました。
今回のエキシビションは、2023年春イタリアで開催された世界最大規模のデザインの祭典『ミラノデザインウィーク』に出展した「楽器がある生活」をテーマに、「見せる(魅せる)楽器」を追求したプロトタイピングを展示。思えば、ピアノはともかくとして、バイオリンやコントラバス、フルートなどは、自宅では「保管」としてケースに収められているのがほとんど。奏でる豊かさのみならず、眺めても得られる至福を感じ取ってほしい、との願いからのデザインたちです。
 楽器あるリビング:『Meow』。バイオリン・セラーがある風景
楽器あるリビング:『Meow』。バイオリン・セラーがある風景

知人宅に訪れ、リビングへ招き入れられて、バイオリン・セラーがあったらとしたら。まずは、収められているバイオリンに目に行くことでしょう。アイボリーの革に縁取られて、まるで額装された絵画のように。でも、だんだんとなにかのように見えてきます。やがて差し込む西日が映し出すシルエットに気がつきます。何か気配を感じて。
背中に立てた弓を尻尾にして、そこにいるのは、猫!
バイオリンには、子ども用のサイズもあって、それは「分数バイオリン」と言われるそう。大人用のフルサイズを「4/4」に、「3/4」「1/2」「1/4」「1/8」「1/10」「1/16」と7サイズあって、2歳からバイオリンを始められるのだ。もし『Meow』にも、各サイズが用意されていて、順序よく並べ置かれていたら、かなりかわいい。
 コンサートホールにあってもいい、『Lean on me』。コントラバス・レストは頬杖をついているかのよう
コンサートホールにあってもいい、『Lean on me』。コントラバス・レストは頬杖をついているかのよう

コントラバスは大きく、安定させるため横にして置きたいもの。コンサート・ホールでは、開演時にも、終演後にも、コントラバスは横たわっていたり、椅子にもたれたりしています。一昨年に体感したNHK交響楽団のコンサートでも、そうでした。

コントラバスは、必ず向かって右側を下にします。それには理由があって、表と裏の板をつなぐ「魂柱」が共鳴箱の中にあって、それは接着されずに“挟まれて”表裏共振をさせている大切なパーツ。右側を下にしないと、外れてしまうそう。
見せつつ、しっかりと保管もしたい。そこで傾けて立たせてみたのが『Lean on me』。コントラバスが、頬杖をついて「弾いてくれよ」とでも話しかけているように見えてきます。演奏時には座ることもできるスタンドですから、「弾いてよ」と言われれば弾かざるを得ないかもしれません。リビングにあったら、訪問者からのリクエストが多くなりそうです。
コンサート・ホールにあったとしたら、開演前に出迎えられているようで、終演後には見送られているようで、大らかに頬杖ついて様子に、期待感と余韻を、より深く感じてしまいそうです。
 『Leave it to me』は、小さなフルーティスト。
『Leave it to me』は、小さなフルーティスト。

フラクタルな三角形の連なりあるシルバーのベースが美しい。この三角形は、フルーティストが奏でるときの腕のかたちから。だから副題は「Tiny Flutist」。
フルートは、真ん中に重心があって、重さを感じさずにリラックスして演奏されるそう。だから、シルバーベースには、奏者のように二点を支えにして、バランス宜しく、リラックスして佇んでいます。その姿は、オブジェのようであり、奏者とフルートが一体となっているようにも見えて、奏でられる音色まで聞こえてきそうです。
 伝統への敬意、その本質を知り得て、革新をすること
伝統への敬意、その本質を知り得て、革新をすること
ヤマハデザイン研究所には、1987年に制定された5つのフィロソフィーがあります。
「本質を押さえたデザイン」
「革新的なデザイン」
「美しいデザイン」
「でしゃばらないデザイン」
「社会的責任を果たすデザイン」
それぞれの言葉の意味を咀嚼し、解釈を深めては「ヤマハらしさ」をかたちにしてきました。
数世紀前に、そのかたちを完成させて機能美を有する楽器。使われる素材、共鳴構造などから自然楽器とも言われることあって、ある意味で「自然の摂理」の沿ったデザインを持ちわせていますし、特にクラシック音楽では「再現」を求められますから、楽器の本質を押さえなくてはいけません。
現・研究所所長の川田 学さんに「伝統と革新」について伺ってみました。チェンバロから発展したフォルテ・ピアノの革新性を例にして伺ったのです。
「チェンバロとフォルテ・ピアノの間で甲乙つけるのではなく、チェンバロだからこそ、フォルテ・ピアノだからこそと、そしてモダン・ピアノへと、それぞれがあってこそです。チェンバロが古いからと、決して否定はできないものです」。
“だからこそ”と、存在する意義や本質を思考する一端を垣間見た気がしました。「革新」は容易ではありません。長年培われた道具であれば、なおのこと。
「伝統」を制約と捉えずに、今にできること。電子ピアノやサイレント・シリーズでは、その原型である自然楽器へのモチーフやオマージュにとどまらずに“本質”を押さえると同時に、現代の技術のエレクトロニクスとを融合させています。
そう。チェンバロからフォルテ、モダンと発展したピアノのように、過去を否定するのではなく。

そして今回は「見せる」という楽器の在り方への提案。道具と人と技術の良い関係をかたちにしています。
機能美の究極な姿を持つ楽器を愛でる。楽器の弾き語りに、心が動かされるように、佇まいからも、心地よさを感じてほしいとの願いを込めたデザインたち。帰路に読む、今回のエキシビションのパンフレットには川田さんの「人々の感性に訴え、感動に繋がるデザイン。『ヤマハらしさ』を追求し続けます」との言葉があります。
 機能美は、そこに在るだけで。
機能美は、そこに在るだけで。
逗子での会話は、時間がすぎるのを忘れるように続いていた。
テーブルに置かれた数冊の書籍を手に取って「本にも機能美があります。活字を印刷し、綴じられて、そこに在ります」と、構成と編集という設計して、レイアウトと装丁を施し、読者の心を動かすものとして在り続けるものが持つ機能美を、Fさんは語り始める。
「読むだけでなくて、書架に収めた時の並び、テーブルに置いた時の佇まいにも美を感じさせます」と、続けて「意匠は、受け手の感性に託すことも在りますから、正解が一つではない難しさがありますよ」と。
そして「受け手へ、媚びず押し付けずに、つくり手としての軸が必要ですよ」と告げられたのだった。
Fさんから、書籍づくりについて伺い、ご教授を受けるなかでは、「美」についてとなり、文化や芸術に、やがて道具へと展開しては「機能美」へと至るものだった。
機能を全うするためにつくられたもの。そのために形づくられ、長い間に、細部から進化しても、変わることなく愛されるものには、佇まいも美しさを感じる。人の手によるつくりこみが施されているものなら、なおのこと。
「機能美を見せる」作品たちと、ヤマハデザイン研究所のデザインへのフィロソフィーを、デザイナーの意図を、見て、話を伺っていて、Fさんとの語らいが思い出されました。
*Fさんとは、株式会社 資生堂名誉会長であった福原義春さんです。読書家であり、著書を多く上梓され、「文字・活字文化推進機構」の会長として、書籍をはじめ、活字文化へも力を注がれていました。企業の文化芸術支援(メセナ)を推進され、経営者とともに美を探求する文化人でした。
*メイン写真:ヤマハ株式会社