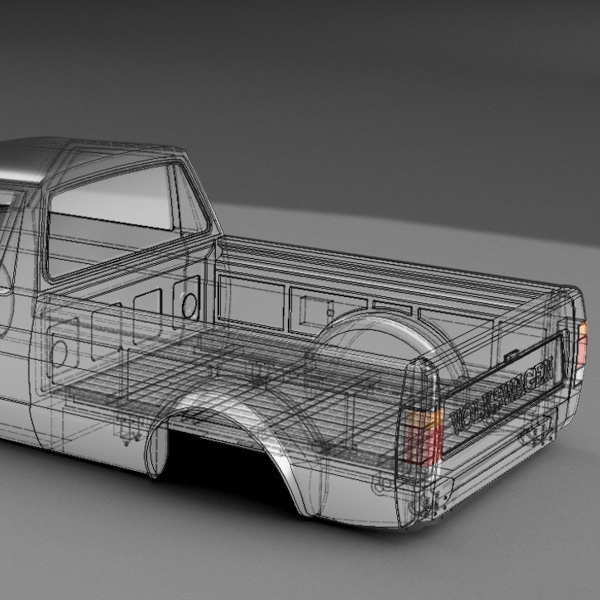大矢麻里&アキオの 毎日がファンタスティカ! イタリアの街角から #08
「アメリ式」あり「デザイン」あり。仏伊ドアノブ考
大矢 アキオ 2023.03.12ものづくり大国・ニッポンにはありとあらゆる商品があふれかえり、まるで手に入れられないものなど存在しないかのようだ。しかしその国の文化や習慣に根ざしたちょっとした道具や食品は、物流や宣伝コストの問題からいまだに国や地域の壁を乗り越えられず、独自の発展を遂げていることが多い。とくにイタリアには、ユニークで興味深い、そして日本人のわれわれが知らないモノがまだまだある。イタリア在住の大矢夫妻から、そうしたプロダクトの数々を紹介するコラムをお届けする。
 フランスで見かける卵型
フランスで見かける卵型
誰もが家で1日のうち何度となく触るものといえばドアの取っ手である。今回はフランスとイタリアにおけるそれを紹介しよう。
筆者がフランスに行くたび、勝手に「アメリ式ノブ」と呼んでいる取っ手がある。握玉と呼ばれる部分が卵型をしているものだ。多くの場合、白い陶器製である。なぜそう呼ぶようになったかといえば、2001年のフランス映画『アメリ』に登場するからだ。パリ・モンマルトルを舞台にしたその作品は、オドレイ・トトゥ演じる女性アメリが主人公である。彼女には知的障害をもつ友人がいて、彼はいつも職場の八百屋で店主にいじめられている。ある日彼女は、店主の住居に侵入。ドアの内側と外側のノブを交換し、店主を混乱状態におとしいれることで懲らしめる。そのときのノブが、まさに白い卵型なのである。
アメリ式ノブは、筆者が泊まるような古い安宿でたびたび発見してきた。パリの語学講師宅にもあった。直近では2023年2月にホームステイしたパリ西郊の家だ。筆者にあてがわれた部屋や、寝室に至るドア、いずれにも付いていた。


見た目は古いが、握った掌のなかで収まりが心地よい。先日は、なんとローマでも遭遇した。場所は、カラヴァッジョの作品が収められていることで有名な「サンルイージ・デイ・フランチェージ教会」だ。真鍮製であるもののアメリ式ノブだ。なぜイタリアにあるのか疑問をもったが、歴史を知って納得した。この施設、16世紀末にローマ在住フランス人のために建立されたものだったのである。ドアノブ自体は後の時代のものであろうが、フランスのテイストを細部まで反映しようとしたことが窺える。
アメリ式ノブについて自動車とアンティーク・トーイのコレクターでもあるパリの知人ディディエに聞いてみると、「第二次大戦前の家やアパルタマンで非常に一般的だったんだ」と教えてくれた。ちなみに、彼の出身地である大西洋岸のル・アーブルでは連合軍による爆撃で街の90%が破壊された。「だから、そうした形状のノブはあまり残っていないよ」と証言することからも、戦前スタイルであることがわかる。



 イタリアの定番
イタリアの定番
アメリ式ノブは部屋用だが、各戸の玄関扉や建物エントランスの屋内側で見かけるのは、写真のような施錠・解錠器だ。フランスだけでなくイタリアでも同じで、以前筆者が住んでいたシエナ旧市街の古い家にも同様のものが使われていた。
室内側からも鍵を差せるもの・差せないもの双方あるが、いずれも側面から延びるノブを引っ張ると解錠する。ノブの代わりに赤いボタンのタイプもある。古い木製の玄関扉でも比較的容易に装着できることから今日でも人気が高い。こちらではアマゾンでも購入できる。


いっぽうイタリアで室内ドア用として頻繁に見かけるノブは、こちらである。商品名を「プレミアプリ・ノーヴァ」という。製造元は、北部コモを本拠とする「セラトゥーレ・メローニ」である。ことわっておくが、綴りはMeroniであって、2022年10月にイタリア共和国首相となったジョルジャ・メローニMeloniと関係はない。同社は1945年の創立当初は家具用施錠器具を製造していたが、1973年にドアノブに進出。プレミアプリ・ノーヴァは1979年に発売した製品で、イタリアを代表する工業デザイン賞「コンパッソ・ドーロ」も受賞している。
premiapriは「押して開けて」を意味する。一般的なドアノブが握玉全体を回すのに対し、握玉は不動だ。代わりに、上部の黒いボタンを押して開ける。セラトゥーレ・メローニの特許だ。鍵穴付きや、内鍵用ターンスイッチが付加されたタイプもある。家庭用以外にも、オフィスの入り口、空港やショッピングモールの化粧室など、さまざまな場所に使われている。
ただし、経年変化でボタンの動作がきわめて固くなっている個体も散見される。筆者もトイレで簡単に開かなくなり、焦ることが年に数回はある。それなりの改良が必要だろう。
それでも気がつけば、すでに誕生から四十数年が経過していることになる。ロングライフ・デザインと十分称することができる。映画『アメリ』に話を戻せば、フランス人が気恥ずかしくなるほど、フランス風情を盛り込んだことが世界的成功の秘密だった。小道具スタッフが取っ手の選択にまで自身のセンスを駆使したことは間違いない。いつかプレミアプリ・ノーヴァも、まさにストーリーの鍵を握る要素としてイタリア映画に登場したら、大きな喝采を送りたいと筆者は思っている。