新しい波に乗る英国発祥ブランド
田中 誠司 ロイヤルエンフィールド・クラシック350・クラシックシグナルズ 2022.06.01日本におけるモーターサイクルの人気急上昇、価格高騰、入手困難のなか、注目を集めているメーカーがある。英国発祥で、現存する最古のモーターサイクル・ブランドである「ロイヤルエンフィールド」だ。
19世紀の末、イングランド中部レディッチという町でロイヤルエンフィールドと名付けた自転車の製造を開始し、1901年に初めてのモーターサイクルを市場へ送り出した彼らは、やがて戦時需要に乗って勢力を拡大。1955年にはイギリスを飛び出して、インドのマドラスに専用工場が建設された。
しばらくは英国とインドの両拠点で生産が続けられたが、英国病と呼ばれる経済危機と日本製モーターサイクルの急速な台頭によって、英国本国での生産は1970年で途絶えてしまう。その後もエンフィールド・インディア社は英国時代の伝統を受け継ぐクラシカルなモーターサイクルの生産を続け、1977年には英国を含む欧州市場に輸出を開始。現在(2022会計年度)の年間販売台数は602,268台におよぶ。これはたとえばハーレーダビッドソンの年間販売が20万台足らずであることと比較すると、中大型バイクの生産量としてはなかなかの規模であることを理解してもらえるだろう。

現在のロイヤルエンフィールドのオーナーはインドのアイシャー・グループだが、ブランディングとエンジニアリングの両面で英国との結びつきを再び強めようとしている。
昔からのレース・ファンなら、「ハリス・ヤマハ」というマシンが世界選手権500ccクラスにエントリーしていたことを覚えているかもしれない。日本人ライダーの新垣敏之選手も走らせたマシンだった。そのシャシー・コンストラクターだった「ハリス・パフォーマンス・プロダクツ」を2015年にロイヤルエンフィールドが買収。現在のラインナップ各車のフレームは、彼らによって開発されたものだ。
並行して2017年には、イギリス・レスターシャーにロイヤルエンフィールド・テクノロジー・センターを開設し、プルービング・グラウンドを含む研究開発部門には100人を超えるエンジニア、デザイナー、テスターらが所属している。
 クラスと価格を超えたクオリティ
クラスと価格を超えたクオリティ
現在、ロイヤルエンフィールドには大きく分けて3つの製品ラインナップがあり、トップには並列2気筒650ccエンジンを搭載する「コンチネンタルGT」「INT650」の2モデルを据え、350ccクラスにクルーザーの「メテオ350」と「クラシック350」、そしてアドベンチャー・バイクの「ヒマラヤ」が販売されている。
その最新モデルにして、「クラシック350」という名のバイクを走らせる機会を得た。
クルーザーであるメテオ350とフレームやエンジンを共用しながら、1948年に発売された「Model G2」のデザインやディテールを受け継ぎ、すでにカスタマイズを済ませたような外観が特徴的だ。
クラシック350には装飾の違いで4つのバリエーションが用意され、カラーリングは合計9種類から選べる。日本ブランドのこのクラスのバイクでは、選択肢が少ないのが悩みどころだが、ロイヤルエンフィールドはモデルあたりの生産台数の多さを活かして個性的なチョイスを用意することに成功している。



今回、PFが試乗したのはミリタリー・バイクとしての歴史を反映した「クラシックシグナルズ」というモデルで、デザートサンドというマットカラーに身を包んでいた。
クラシックシグナルズの特徴のひとつは、ボディカラーに彩られた部分の面積がネイキッド・バイクとしては大きいことだ。フロントとリアに大きなマッドガードを装着し、サイドのツールボックス・カバーも丸みを帯びて大ぶり。ヘッドライト・ケーシングはフロントフォークまで覆い、メーターカバーと一体になっている。
フューエルタンクにペイントされた白いナンバーは、それぞれの車体に固有の数字であり、その脇にある丸いバッジには「MADE LIKE A GUN」つまり銃のように(精巧に)作られている、と穿たれる。ロイヤルエンフィールドの祖先をたどると、二輪車生産を開始する前は拳銃などの小火器を製造していたこともある歴史を反映したものだ。
サンドベージュに包まれたそれらのディテールは、形状が愛らしいだけでなく、品質感も素晴らしいことは、この記事に添付された写真を拡大すれば確認してもらえるだろう。
フレームにも同様なことが言える。元来レーシング・コンストラクターだったハリス・パフォーマンスによるコントロールは、設計だけでなく製造面にも浸透しているようで、作りやすさのために外観を妥協した形跡がなく、溶接もとても丁寧に仕上げられている。



 伸びる国際商品の勢いを感じる
伸びる国際商品の勢いを感じる
ヤマハSRの最終型を昨年夏に入手したばかりの筆者にとって、クラシック350はとても気になるバイクである。実際に走らせてみると、どうだろうか。
日本仕様は2人乗りが標準だが、もともとはシングルシートとしてデザインされている。前後に丸みを帯び、比較的幅が広いシートは、荷重が一点に集中することがないから長距離でも疲れにくい。ハンドルは比較的後方にマウントされているため、コンパクトでアップライト、つまり自然なライディング・ポジションとなる。いわゆる足着き性は良好とはいえないものの、その点を優先するなら兄弟車であるメテオ350が解決してくれるだろう。
エンジン始動のため右手の赤いスイッチを左に回転させてセルフスターターを作動させる。キックスタートしか選べないSRのオーナーとしては羨ましくもある。ABSが標準装着されているのも、ロイヤルエンフィールドのアドバンテージだ。



アイドリングのサウンドは心地よく、振動も控えめだ。ユニット・コンストラクション・エンジン(UCE)と呼ばれる空冷エンジン本体の構造は、2008年から用いられているそうだが、その後厳しさを増した排ガス規制に対応して電子制御燃料噴射式となり、ユーロ5相当の基準をクリアしている。
バランサーシャフトの搭載に加えて、エンジンを抱えるフレームやマウントの構造自体がよく吟味されているのだろう。走り出したクラシック350は、無用な振動を伝えず、トコトコと心地よいパルスとともにクルージング・スピードに到達する。パワーがわずかに20psを超える程度であるから、あまり高速道路でペースを上げることは叶わないものの、349ccという排気量と27Nmという最大トルクのデータから想像する以上に低速トルクに余裕があっていい。
直進安定性も、このエンジンパワーで現実的に到達できる範囲ならしっかりしていて、筆者のSR400よりも横風や路面の不整に影響されにくいから、このクラシカルな外観から想像される水準より、ずっとクルージングは快適だ。
驚く人もいるかもしれないが、このクラシック350の祖先であるロイヤルエンフィールド「モデルG2」こそ、スイングアームを備えるリア・サスペンションを搭載した世界初の量産モーターサイクルだった。リアスプリングの巻数が多いことからも、サスペンション性能への投資を怠っていないことが理解できる。



ロイヤルエンフィールドのインド国外における販売台数は2022会計年度で81,032台と、前年比2倍以上の伸びを記録しているという。これは2021年の日本における251cc以上の小型二輪車の販売台数(83,571台)とほぼ等しい規模である。母国イギリスから技術や伝統を吸収して、国際商品として成長していく過程にあるのだろう。
クラシック350は、低廉な価格から想像する以上の品質を実現し、個性的でありたいという欲求も満たすことのできる、ファッショナブルなシティ・ランナバウトの新しい選択肢だ。日本全国にディーラー24拠点、サブディーラー5拠点と販売網が拡大し、走行距離無制限の新車3年保証が付帯することも書き添えておく。







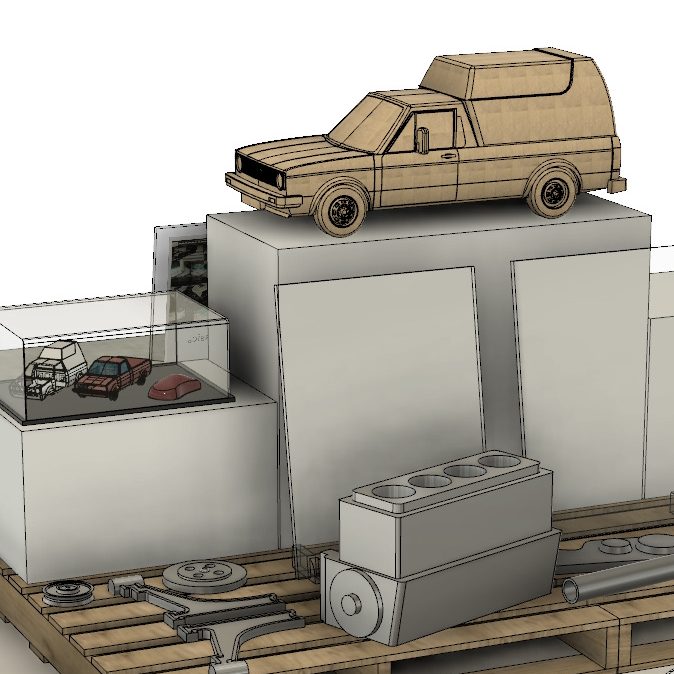













![100年目のアディショナル・インパクト……BMW R1300GS[ケニー佐川の今月の1台・第5回]](https://parcferme.co.jp/wp-content/uploads/2024/02/IMG_7448-1.jpeg)




